エンゲージメント調査(従業員意識調査)は、組織の健全性を測る重要な指標です。その結果をどのように、誰に、どこまで開示するかという問題は、組織改革を進める上で、そして、信頼関係の構築において極めて重要な意味をもちます。
理想はすべての結果を全社員に開示し、全社員で現状を把握し、全社員が一丸となって現状の問題解決に取り組むことでしょう。ただ、経営と従業員の信頼関係が十分ではない状態では、リスクとなる場合もあります。一方で、一切開示をしないという判断もよくありません。結果が悪くて隠蔽しているように見えるからです。
では、どのように開示していくべきか考えていきたいと思います。
開示の対象と範囲を考える
エンゲージメント調査の結果開示は、対象によって慎重に検討する必要があります。エンゲージメント調査をはじめて実施した年は、以下のような開示が良いと思っていますが、もちろん社風や普段の業務の進め方等にもよります。
- 社内(役員層):全体像と詳細な分析
- 社内(幹部職):全体と担当部門の詳細データ
- 社内(一般社員):全体概要と所属部門のデータ
- 社外(IR):選択的な開示と簡単な対応策
エンゲージメント調査の開示方針と企業の姿勢
私がエンゲージメント調査(従業員意識調査)をはじめた18年ほど前は、まだ社外に結果を開示するという考え方はほとんどありませんでした。実施する企業は、あくまで社内の問題改善に使うという目的が大半でした。しかし近年では、企業の実施背景も多様化しています。
- 1. 社外開示を前提とした調査
-
人的資本経営への注目から、人的資本開示を前提とした調査実施が増えています。このような場合は社内の改革には使いにくい場合もあります。また、社外開示前提の調査は、委託企業が設計している設問項目によっては、どうしても結果を良く見せようとするバイアスがかかりやすくなります。
- 2. 現状把握のみを目的とした非開示型調査
-
人的資本開示はしないが、実施企業が増えていることで、耳にする機会も多くなり、当社でもとりあえずエンゲージメント調査をやってみようかなという形で、純粋な「現状把握」のために調査に取り組む企業も増えています。このような場合、実際に当社がお付き合いした企業の中にも、「えっ、調査なので、現状把握だけだと思っていました…社員への開示か…考えてもいませんでした。」という反応を示すケースもありました。
社内開示の重要性と注意点
どのような目的でエンゲージメント調査を実施するにせよ、従業員に回答してもらうという事実は変わりません。回答者は調査に協力した以上、その結果に関心を持つのが自然です。実際に調査実施企業で「結果の開示に関心があるか」と問うたところ、7割以上が関心を示したという事実もあります。
透明性がもたらす信頼の基盤
基本的な姿勢として、開示レベルに段階を設ける必要はあるものの、極力開示する方向で検討することが大切です。本質的には透明性が高いほど、経営と従業員の間の信頼関係は強化されます。
信頼関係が構築されていれば、機密情報など開示できない情報があった場合でも、その判断自体に対する信頼も高まります。つまり、日頃の透明性が「開示しない」という例外的判断への理解にもつながるのです。
ハンドリング可能な範囲の見極め
「誰に何を見せるか」という開示レベルには配慮が必要です。たとえば、ある部署の社員に他部署の詳細データを見せる必要があるのか、という点です。自らがハンドリング可能な範囲のデータに留めるのか、それとも参考として関連性の低い部門のデータまで開示するのか。これにはメリットとデメリットの両面があります。
自由記述の取り扱いに要注意
特に注意すべきは自由記述の取り扱いです。批判的な記述には自然と注目が集まりやすいものです。中には、実際の批判的記述が少ないにもかかわらず「批判的な意見が見当たらない=隠蔽している」と誤解されるケースもあります。
自由記述の取り扱いを誤ると、本質的な改善点の議論ではなく、単なる「見世物」として捉えられてしまい、建設的な活用がなされない恐れがあります。批判的意見を娯楽的に消費してしまうという状況は、本来の目的からかけ離れた「ゴシップ的関心」を生み出してしまうことになります。
結果開示と改善活動の循環
エンゲージメント調査が単なる数値収集ではなく組織変革のツールとして機能するためには、結果の適切な開示と、それに基づく改善活動が不可欠です。調査を実施するたびに、結果と取り組みを適切に開示し、対策を考えていくサイクルを回すことが極めて重要です。
このサイクルが機能してこそ、エンゲージメント調査は組織と個人の成長に貢献する有意義なプロセスとなります。透明性のある結果開示は、調査の信頼性を高め、回答者のモチベーションを向上させると同時に、経営と従業員の相互理解を深める基盤になります。





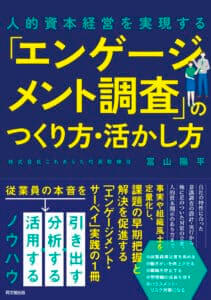

コメント