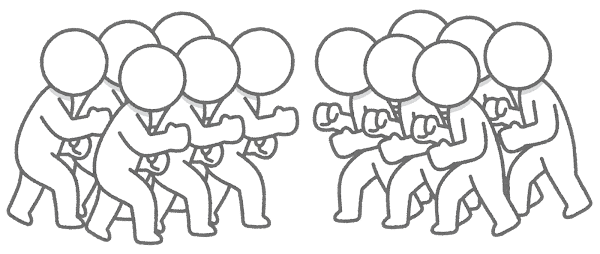-

GmailのPOP3受信終了への対応:独自ドメインメールの転送設定
Googleは2026年1月でGmailのPOP3受信機能を終了することを発表しました。これまで独自ドメインのメールアドレス(以下「メールアドレスA」)をGmailで受信していた方は、代替手段を検討する必要があります。 本記事での説明は、わかりやすくするために... -
Microsoft 365 で Teamsがないプランに変更したら意外と影響が出てきた話
Microsoft365自体は、2016年の秋から使っていて、だいたい9年くらい使っています。 2020年にTeamsがあったプランから、Teamsなしの純粋な基幹アプリだけのプランに切り替えたのは覚えているのですが、それ以降、こちらはプランを変えていなくても、プ... -
職場飲み会って設定する必要があるのだろうか?
「冨山さん、職場での飲み会って定期的にやったほうが良いかな?私が若いころは毎日のように連れて行かれたものだけど、もちろんそんな時代じゃないことはわかっている。かといって、まったくしないというのも…どうしたらいいのだろうか?」 クライア... -
“幼さ”の正体:価値観の押し付けから見えてきたもの
先日、大学院時代の同期と話していて、「幼いとはなんだろう?」という質問をしたところ、間髪入れず 幼い人とは、自分の価値観を押し付ける人 という明瞭な回答が返ってきました。この答えはすぐに腑に落ち、幼い高校生、幼い社会人、幼い上司、幼い部... -

エンゲージメント調査の結果を社内に開示する意義
エンゲージメント調査(従業員意識調査)は、組織の健全性を測る重要な指標です。その結果をどのように、誰に、どこまで開示するかという問題は、組織改革を進める上で、そして、信頼関係の構築において極めて重要な意味をもちます。 理想はすべての結... -
焦りが生む風土改革の誤解 – 短期対応と長期変革の両立
風土改革が求められる背景には、多くの場合、組織が直面する大きなトラブルや危機があります。たとえば、重大な品質事故の発生、コンプライアンス違反の発覚、従業員のメンタルヘルス問題の増加、離職率の急上昇、顧客満足度の著しい低下などです。こう... -

中小企業が見落としがちな10のセキュリティリスク ~専門家が警告する意外な盲点~
サイバーセキュリティというと、大企業や政府機関を標的にした派手な攻撃が注目されがちですが、実は中小企業や小規模事業者も深刻なリスクにさらされています。さらに重要なのは、一社のセキュリティ不備が取引先全体に波及する可能性が高いことです。 ... -
経営の”いい”スピード感と”見直したい”スピード感
めまぐるしく変わっていく時代、あらゆる課題にスピード感をもって取り組んでほしい。 このようなスピード感を上げてほしいというメッセージが経営から発生されるのは、現代のビジネス環境において珍しくありません、というより、当たり前のことでしょう... -

人と会う数を増やすことで生まれる「気づき」
「冨山さん、それで人見知りなんですか!?」とよくいわれますが、私は自分で人見知りだと思っています。知っている人が一人でもいる場であれば対応できますが、まったく知り合いがいない場に参加するときは、移動中など、お目に掛かるまでの間はかなり緊... -

風土改革の中心メンバーのための心得:批判的な意見の背景を考える
風土改革で、色々と意見を吸い上げた上で、改革方針を明確にして、ワーキンググループやタスクフォースを作って進めても、批判的な意見で、気持ちが萎えてしまう経験ありませんか?風土改革に中心的に関わったメンバーであれば、誰もが経験したことがあ...
冨山陽平のブログ
日常の業務を通じて知り得たこと、感じたことを書いています。